産業革命について10回目の記事になります。
今回は「ジェントルマン資本主義」について見ていきます。
[この連載の記事一覧]
前回まで、産業革命の歴史的意義、つまり影響をいろいろ見てきました。
とくに8回目の記事では、「産業革命によってイギリスが覇権国家となった」と書きました。
つまり、
イギリスは最初に産業革命を達成したことで、「世界の工場」となり、大量の製品を売って富をたくわえた。こうした経済力を背景に、さらなる輸出先市場をもとめて植民地を獲得していき、19世紀にはイギリスを中心とした大英帝国が誕生して、世界の覇権をにぎった。
と、昔は考えられていたんです。
(歴史の流れを説明した記事でも、説明が複雑になるんでこの説を採用しています)

ところが、1970年代からイギリスの歴史学者を中心に、「どうもそうじゃないらしい」と主張されはじめました。
イギリスが覇権を握った理由は産業革命なんかじゃない、もっとほかにあると。
その主張の代表格が「ジェントルマン資本主義」という考え方なんです。
つまり「ジェントルマン資本主義」とは、産業革命の歴史的意義は従来言われていたほど重要じゃなかった、と主張するものなんですね。
そこで、この「ジェントルマン資本主義」とはどういう考え方なのかを、産業革命の記事の最後として見ていこうというわけです。
けっこう複雑な話になりますが、できるだけわかりやすく解説していきます。
読者の方は「大学で歴史を専攻すると、こんなことも学ぶんだ」とでも感じてもらえれば幸いです。
「ジェントルマン資本主義」の定義
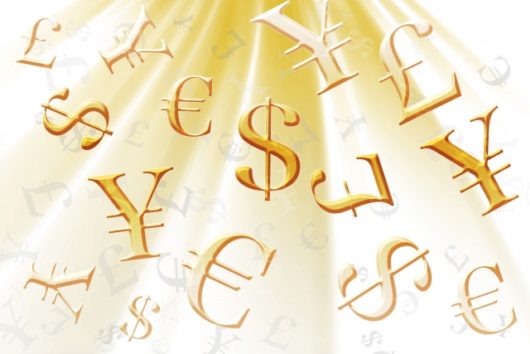
ジェントルマン資本主義とは、近代イギリスの非産業的な経済活動を指します。
「非産業的」とはつまり製造業以外ということで、金融や貿易、サービス業などのことです。
より具体的にいうと、銀行や証券会社、商社や海運会社、保険・投資会社など、モノよりもカネをおもに扱う業種です。
これらの業種にたずさわる金持ちたち、つまり金融資本家が、産業革命後もイギリスの政治・経済を動かしていった。
金融資本家の影響は、産業革命によって勃興した資本家、つまり産業資本家たちよりも大きかった。
だから19世紀のイギリスが植民地をたくさん獲得した理由も、当時のイギリス経済(=イギリス資本主義)の実態も、そしてイギリス帝国主義の性質も、金融資本家たちを中心に考えればうまく説明できる。
こうした主張が、「ジェントルマン資本主義」の言わんとするところの中心部分なんです。
そして、19世紀の金融資本家たちとは、じつは地主ジェントルマンが移行したものでした。
だから「ジェントルマン」資本主義という名前がついたんですね。
名付けたのはイギリスの歴史学者、ケインとホプキンズという2人です。
では、こうした主張はどのように出てきたのか?
旧来の「産業革命によって産業資本家が生まれ、かれらがイギリス政治・経済の中心となって大英帝国をつくった」という主張はどこがダメだったのか?
これらの点を、1970年代以降のイギリス歴史学の推移にそって見ていきましょう。
「ジェントルマン資本主義」という考え方が出てきた経緯

問題の所在をもういちどハッキリさせときます。
「19世紀にイギリスの経済が大発展し、世界の覇権をにぎるまでになったのは、産業革命による製造業のおかげなのか」という点です。
製造業よりも金融業がイギリス経済の中心
1960年代まで、イギリスの歴史学者たちはこの問いにたいして「Yes」と答えていました。
でも1970年代から徐々に、「No」と答える歴史学者が出てきました。
というのも、「製造業ではイギリスの発展が説明できない」事実がいろいろ見つかってきたからです。
たとえば他国の製造業の発展。
19世紀にはフランスやアメリカも産業革命を果たし、製造業がイギリス並みかそれ以上に発展しました。
つまりイギリスの製造業における優位性なんてなかったんですね。
イギリスはただ「最初に産業革命がはじまった」というだけのことだったんです。
また19世紀のイギリスの貿易収支。
製造業だけでみると大赤字だったんです。
それを金融や貿易などの利益で補うことで、トータルすると黒字になってたんですね。
それから19世紀のイギリスの富裕者リスト。
いわゆる長者番付ですが、製造業者は意外に少なかったんです。
それよりも地主と金融業者と商人が上位を占めてたんですね。
また地域別にみると、リヴァプールやマンチェスターなどの北部より、ロンドンをはじめとした東南部に富裕者が多いこともわかりました。
これらの事実から、19世紀のイギリス経済の中心は、北部の製造業よりも東南部の金融・サービス業だったのではないか。
そして金融・サービス業におけるイギリスの優位性こそが、イギリスが世界の覇権をにぎった理由ではないかと言われはじめます。
シティの存在が強調されはじめる
とくに金融・サービス業の中心地として、ロンドンのシティに歴史学者たちは注目しはじめます。
「シティ」とは「シティ オブ ロンドン」の略で、ロンドンの中心です。
東京都における中央区、ニューヨークにおけるウォール街みたいな存在です。
このシティは19世紀以降、イギリスの金融・サービスの中心地として発展しました。
証券取引所やイングランド銀行などがあって、いまなお世界経済の中心のひとつですね。
イギリス経済の中心が金融・サービス業ならば、シティこそイギリス経済の中心地だ。
じゃあシティを動かす人々が19世紀のイギリス経済を、ひいては19世紀の世界を動かしていたことになる。
いったい、シティで金融・サービス業を担っていたのはどういう人々だったんだろう?
歴史学者たちがこう考えるのも当然です。
そして1986年、ケインとホプキンズという2人の歴史学者が画期的な回答を提出するのです。
「シティの金融・サービス業を担っていたのはジェントルマンたちである。かれらの動向と利害によって、イギリスは世界の覇権国家となったのだ」と。
金融ジェントルマンの誕生
「え?でもジェントルマンって地主のことでしょ。なんで金融・サービス業者がジェントルマンに含まれるわけ?」
こうした疑問ももっともです。
4回目の記事でみたように、ジェントルマンとは土地を持ってる有閑階級の人を指しますからね。
でもケインとホプキンズいわく、「ジェントルマンの中核は地主から金融・サービス業者に移行した。つまり19世紀後半以降のジェントルマンとは金融ジェントルマンを指すのだ」ということなんです。
かれらの説明をもうちょっとくわしく見てみましょう。
まず19世紀後半の金融・サービス業者の内訳ですが、イギリスの富裕者リストには、銀行の取締役、個人銀行家、個人投資家、貿易為替手形引受業者(マーチャントバンカー)、貿易会社や保険会社や船舶会社の社長、金属・鉱山業の経営者などが名を連ねていました。
企業名を挙げるなら、イングランド銀行、ロスチャイルド商会、ロイズ保険組合などです。
(ちなみにロイズ保険組合は世界的にもユニークな保険会社です。くわしく知りたい人はこちらのマンガをどうぞ)
こうした職業の富裕者たちは、共通の生活様式をもっていました。
肉体労働をしないこと、政治に積極的に関わること、子どもをパブリックスクールからオクスブリッジへ進学させること、ティータイムには砂糖入りの紅茶を飲むこと等々。
これ、4回目の記事で見たように、「ジェントルマンであること」の要素なんです。
つまり、19世紀後半の金融・サービス業に携わる富裕者たちは、ジェントルマンの仲間入りを果たしたんですね。
こうして、旧来の地主ジェントルマンに金融・サービス業者を加えた、新たなジェントルマン階層が誕生しました。
また旧来の地主ジェントルマンのなかにも、より積極的に金融商品を取り扱ったり、地代収入から保険料収入へ切りかえたりする者も多く現れました。
なぜなら1820年代からイギリス政府が自由主義的政策を打ち出したことで、地主ジェントルマンの既得権益が脅かされていったからです。
結果として、19世紀後半には、ジェントルマンの中核は「地主」であることから「金融・サービス業者」であることに移行したんです。
ちなみに8回目の記事で、「イギリスの自由主義的政策によってジェントルマンが力を失ったわけではない」と書いた理由も↑これです。
以上がいわゆる「金融ジェントルマン」の成立の理由です。
ここまでのまとめ

こうして、
- イギリス経済の中心である金融・サービス業
- 金融・サービス業の中心地であるシティ
- シティの中心メンバーである金融ジェントルマン
という3つの材料が整いました。
ケインとホプキンズはこの3材料をもとに、19世紀のイギリス帝国主義を説明しなおすんです。
産業革命という材料はぬきで。
これが「ジェントルマン資本主義」論です。
ではシティのジェントルマンたちは金融・サービス業を通じて世界とどう関わっていたのか?
つまりインドやアフリカや東南アジアなど、イギリスが世界中に植民地を広げていったのは、金融ジェントルマンの利害とどう関係しているのか?
この点を次回、具体的にみていきます。
→ジェントルマン資本主義によってイギリスが「世界の銀行」になった
*参考文献(未紹介のものに限る)
秋田茂編著『パクス・ブリタニカとイギリス帝国』ミネルヴァ書房、2004年
歴史科学協議会「歴史評論」1998年5月号







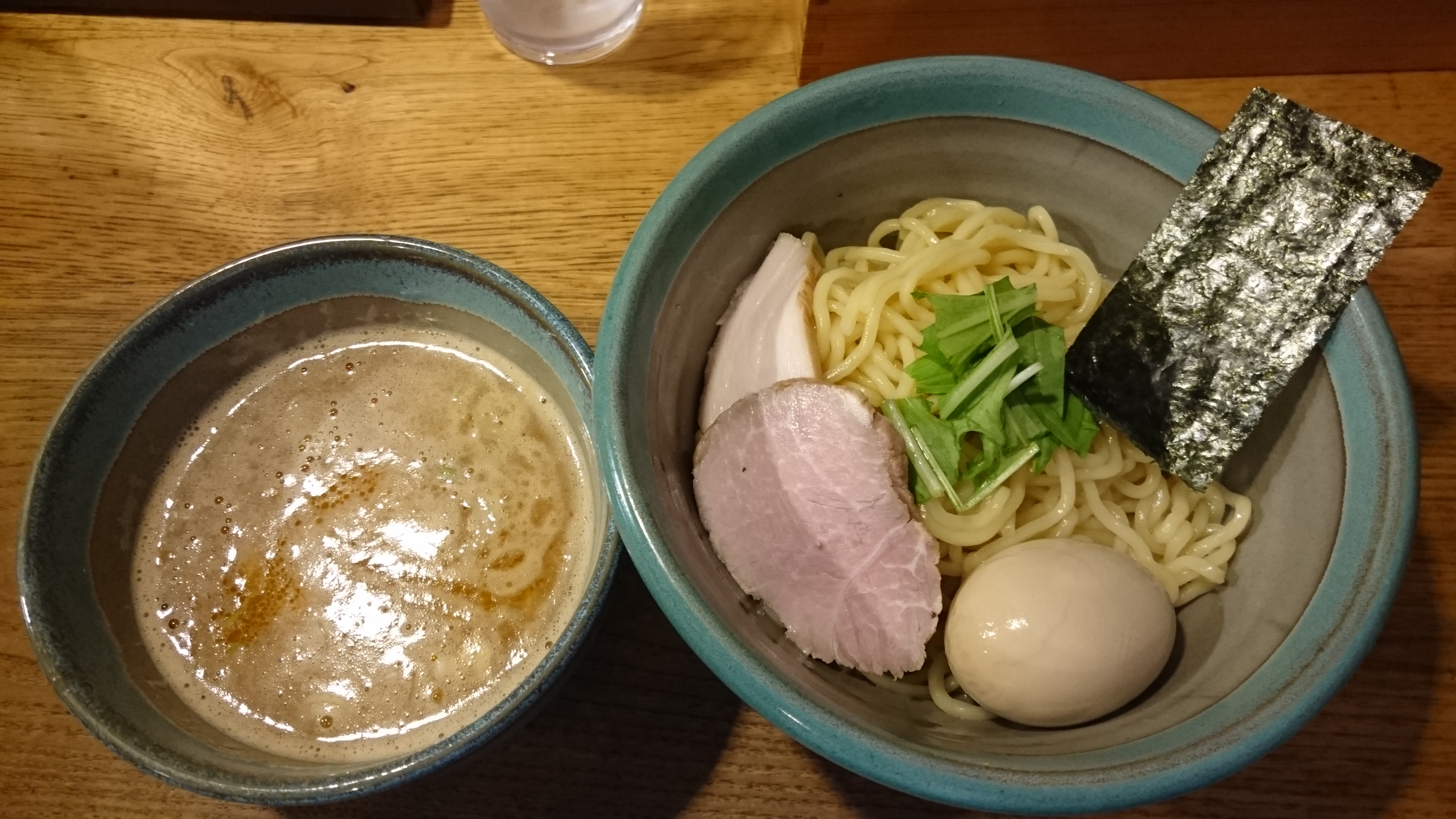
コメント